し、置換土上には砕石4号を用いて基礎マウンドを作成した。マウンド上に函体を載せ、さらに函体設置後に背後地盤を水中落下法により作成した。
4. 実験結果と考察
4−1 実験模型被災状況
(1)現象再環実験:Fig-5に模型実験によるケーソン式岸壁の変形状況(実物スケール)を示す。これより函体背後地盤は、函体背後において沈下量が大きく、函体から離れるに従ってほぼ一定値となり、また函体の海側への移動(函体天端で約2.3m)に伴って、背後地盤も水平方向に移動していることがわかる。主働崩壊に伴う地表面でのクラックは観測されていないことから、背後の埋立土地盤が沈下しながら海側へ連続的に移動したものと推定される。函体は捨石マウンドにやや沈み込み、マウンド全体が置換土層に沈み海側に移動している。従って、本実験における函体の海側移動は、設計時に考慮しているマウンドと函体間の滑動だけではなく、マウンドおよび置換土の変形に伴う移動と考えられる。この結果は運輸省第三港湾建設局3の地震後の水中測量結果(Fig-6)と整合するものである。
(2)設計震度相当加振実験:ケーソン天端の水平変位は28cmと小さく、沈下量も10cm以下(Fig-7)となっており、無被害と判断されるこの際に変形量が小さいため、マウンド及びマウンドと置換土層境界のターゲットの変位は計測不能であった。
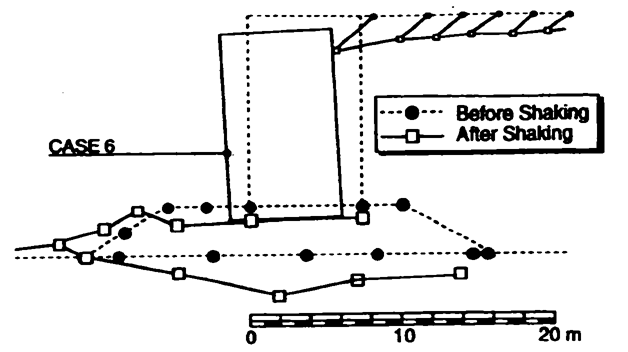
Fig-5 Deformation of a model quay wall(CASE6)
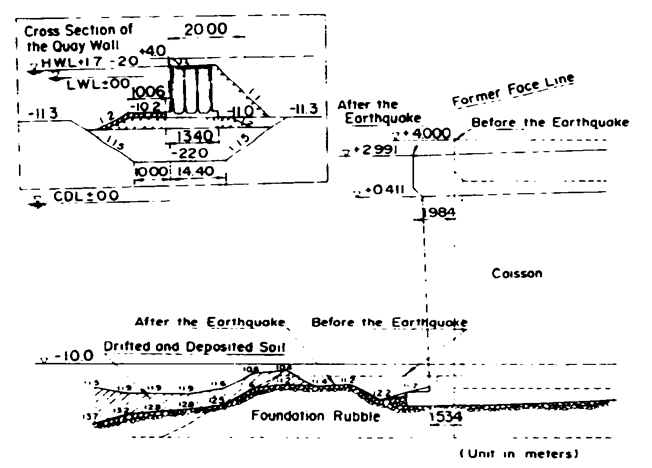
Fig-6 Defomation of rubble mound beneath the caisson
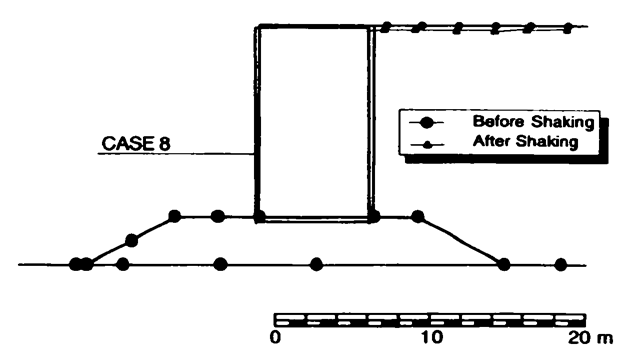
Fig-7 Defomation of a model quay wall(CASE8)
4−2 加速産・過剰間隙水圧・ケーソン変位応答
Fig-8,Fig-9に現象再現実験、設計震度相当加振実験の加速度・過剰間隙水圧・ケーソン変位の時刻歴を示す。
(1)現象再現実験:函体はロッキング運動をしながら沈下・水平移動をすることが、函体天端の加速度波形(A5)より読み取れる。また函体天端の加速度応答は、函体直下地盤の加速度応答(A3)との相関が良いが、函体の変位応答は函体下部および背後地盤の過剰間隙水圧(以下、水圧と呼ぶ)の応答に一致している。従って、函体の変位は水圧上昇による地盤の軟化と強い相関があることがわかる。さらに水圧の応答を詳細に見ると、背後地盤(W5)の水圧は時刻約10秒にほぼ一定値になるが、函体直下(W2)では約5秒程度遅れて一定値になる。さらに函体前面地盤(W7)では時刻約10秒に一度ピークが生じるが、その後約10秒間は水圧が一時的に減少する。これは、函体下部地盤(W2、W7)の水圧上昇が遅れている時間幕に函体が大きく移動してしていることから、その遅れは水圧上昇による置換土の軟化に伴い大きなせん断変形が生じ、正のダイレイタンシーが発生することに起因していると考えられる。さらに函体前面地盤の水圧(W7)は一度減少しているが、これは特にこの部分の地盤が大きなせん断変形を起こしているためと推定される。一方、函体直下地製(W2)の水圧は遅れはあるものの減少はしていない。これは函体直下は函体の自重のために函体前面地盤に比べて大きな上載圧が作用しているため、地盤の軟化程度が小さいことに対応していると考えられる。
函体下部地盤のせん断変形は、函体下部の過剰間隙水圧比(過剰間隙水圧/有効上載圧:液状化の程度を示す指標)が0.4〜0.6程度と完全液状化とは言えない範囲であるため、下部地盤の完全液状化が要因とは言えない。函体直下地盤では有効上戦圧が大きく、さらに常時に作用している初期せん断応力が存在するため、地盤が完全液状化する前にせん断破壊を起こしたものと推察される。
(2)設計震度相当加帳実験:函体の運動は、絶対量は現象再現実験と比較して小さいが、ロッキング運動しており、函体天端の加速度波形(A5)と背後地盤地表(AH9)との相関が認められる。(AH9)の加速度波形で
前ページ 目次へ 次ページ